宮本 悟ゼミ
Satoru Miyamoto seminar
演習テーマ『生活・労働問題と社会保障』
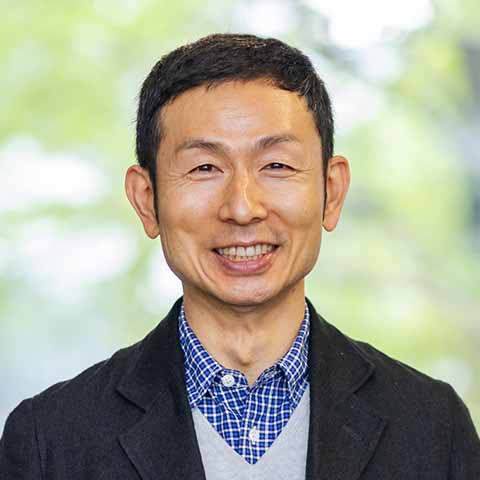
演習テーマ『生活・労働問題と社会保障』
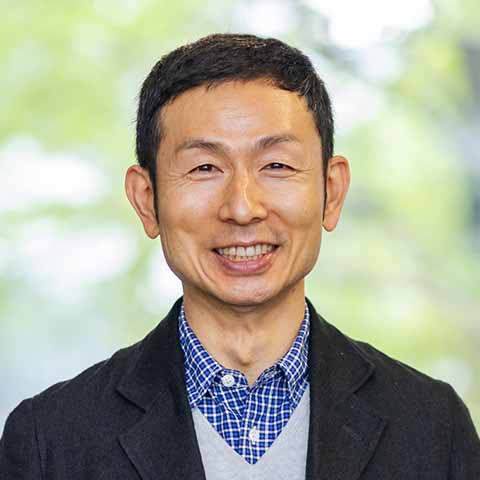
2年ゼミの主要課題は、社会保障の基礎理論を身につけることです。そのため、社会保障理論の基本書をゼミ生全員で輪読することがゼミ活動の中心となります。毎回、1~2名のゼミ生が報告者となり、担当する章の①レジュメ作成、②概要説明、③関連学説の紹介等を行います。その他のゼミ生は事前にテキストを読み込んだ上で質問を用意することが義務づけられており、その質問をめぐって報告者を含むゼミ生同士の議論が展開されていきます。また、関心のある社会保障問題をテーマにしたゼミレポートの執筆も進めてもらいます。今年の各種イベントとしては、6月のゼミ対抗スポーツ大会や8月の栃木県那須塩原市合宿などがあり、親睦をより一層深めることができました。さらに、後期は学外プレゼン大会に参加する予定です。
3年ゼミでは、学内外のプレゼン大会への参加を視野に入れて、ゼミ論文作成を活動の中心に据えます。具体的には、まず、自分たちの関心に基づいて共同研究テーマを設定した上で文献研究・実態調査などを進めていきます。そして、その成果を基にして、各種大会における報告の柱となるゼミ論文をゼミ生一人ひとりが分担執筆していきます。今年度は、「ふるさと納税」・「地方移住」・「フレイル予防」など、今日的問題を取り上げて理論的・実践的視点から考察を加えています。3年次の行事としては例年、夏休み中の2・3年合同合宿、11月の学内プレゼン大会の他に、学外プレゼン大会が予定されています。
4年ゼミでは、全員が卒業論文を執筆します。活動内容は、各ゼミ生が個別に執筆する卒業論文の途中経過を発表し合い意見交換をする、というものです。卒業論文作成のペースメーカー的役割を期待して、4月から年末まで定期的に集まることになります。
入ゼミ時に交わされる約束事は4点(無遅刻無欠席皆勤原則・卒論提出など)ありますが、ゼミ運営に関しては「ゼミ生の主体性を尊重する」という基本方針が掲げられています。