古市 将人ゼミ
Masato Furuichi seminar
演習テーマ『財政の視点から社会経済問題を考える』
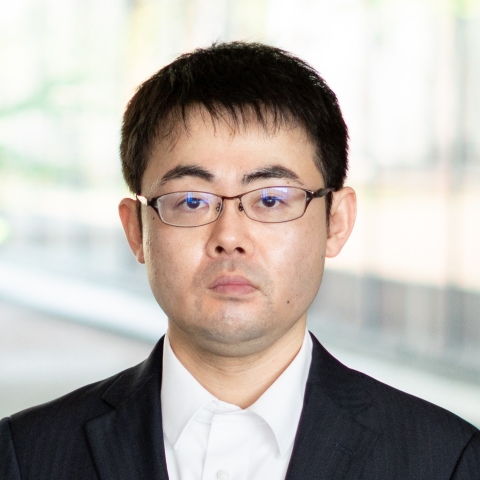
演習テーマ『財政の視点から社会経済問題を考える』
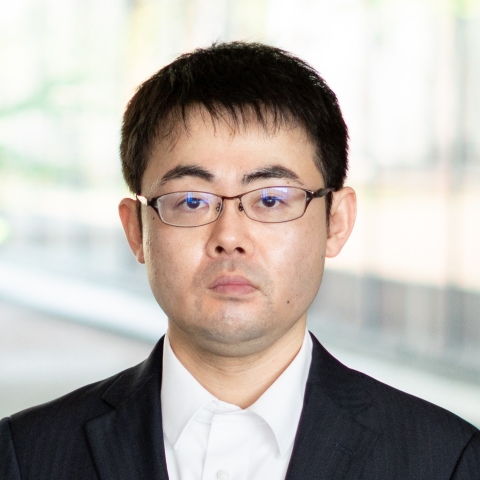
古市ゼミは2025年度に開講されたゼミです。本ゼミは、日本の社会経済問題について財政の視点から検討します。財政とは、政府によるお金の使い方(支出)と集め方(税金など)といった経済活動を指します。私たちは日々、公的なサービスを利用しています。たとえば、道路や教育、医療などは公的な資金で支えられています。
財政の仕組みは、その国がどのような社会問題や経済問題に力を入れているかを示しています。たとえば、教育に投じられる公的資金の金額は国によって異なります。医療サービスを利用するときの自己負担も国によって異なります。なぜ、このような違いがあるのでしょうか。財政研究には、財政がその国の社会状況や政府と人々との関係を反映していると捉える考え方があります。
たとえば、政府が医療費の自己負担の見直しを提案するとします。この政策の提案から導入までの経緯を調べることで、政策の根拠や背景にある社会問題を理解することができます。しかし、政策への反対が強く、政策が導入されない場合もあります。そこには、政府への信頼、制度への満足・不満、他者への信頼・不信、政策決定の納得感など、社会のさまざまな側面が表れます。こうした財政への支持や反対の背景を分析することで、社会の状況や政府と人々との関係を考察することができます。
政府による公的な資金の使い方と集め方に注目する学問を財政学といいます。国や地方自治体の財政を検討することは、その時々の社会問題や経済問題の複雑さや背景を理解するための重要な手がかりになります。本演習では、このような視点から現実の社会経済問題を取り上げ、統計や政策資料などを読み解きながら、議論・発表を通して考察を深めます。
参加者の興味・関心を踏まえて、演習を運営する予定です。詳細はシラバスを見てください。基本的には、以下の通りです。
演習1(2年次)では、課題文献の輪読を通じて、各自の問題意識を深め、プレゼンテーションやグループワークの基礎を学びます。実際の分析例をもとに、社会経済問題の分析方法を身につけます。
2025年の演習1の前期では、宿泊税・訪問税・森林環境税などの地方税や、ベーシックサービスに関する文献を読みました。地方自治体が新しい税を導入する際の課題や、その正当化の理屈、財政の役割などを検討しています。現在は、財政学の入門書を輪読し、基本的な知識を学びながら、社会経済問題を財政の視点から考察しています。
演習2(3年次)では、再分配政策をテーマに文献を読み、分析方法の基本を学びます。これまでに学んだ手法を活かし、経済・社会問題に関する討論を行います。夏に開催される他大学との合同ゼミでは、グループごとに研究成果の一部を発表します。演習2の後期では、財政と社会の関係を扱った文献を読み、各自の問題意識を深めます。前期からのグループ課題を完成させたうえで、各自が自由に設定したテーマについてプレゼンテーションを行います。
演習3(4年次)では、これまでの勉強の成果を活かして、演習論文の執筆に取り組みます。
財政に関心のある人はもちろん、社会問題に関心のある人も歓迎します。文献の輪読、研究、発表に自信がない人もいるかもしれません。心配はいりません。少しずつ慣れていけば、必ずできるようになります。