陳 希ゼミ
CHEN Xi seminar
演習テーマ『中国の歴史と文化から現在社会を読み解くーー東アジアを視野に世界を考える』
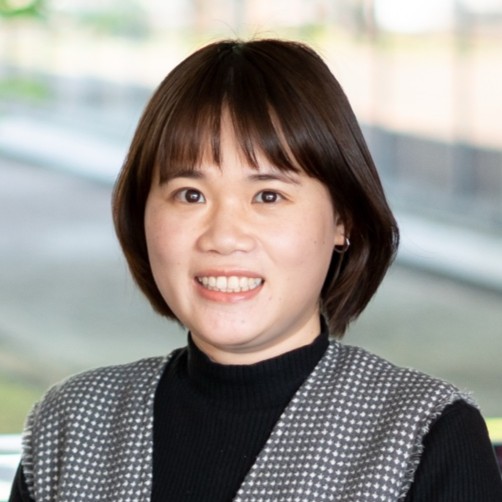
演習テーマ『中国の歴史と文化から現在社会を読み解くーー東アジアを視野に世界を考える』
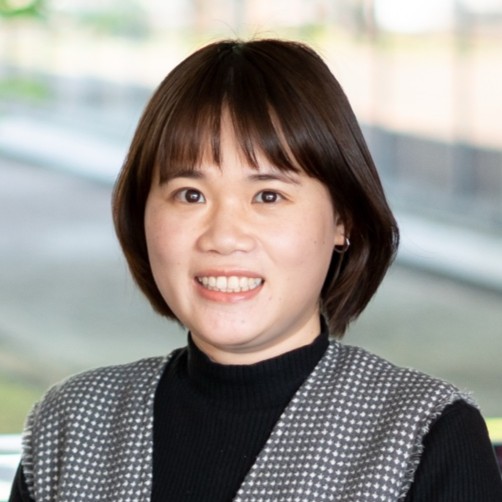
みなさんは「中国」と聞いて、どんなイメージを持つでしょうか。
中国は日本のすぐ隣にあり、古くは遣隋使や遣唐使の時代から、千年以上にわたってさまざまな交流を続けてきました。長い歴史のなかで両国の間には多くの出来事がありましたが、経済や文化を通じた関係は今も途切れることなく続いています。
今日では、グローバル化が進む一方で国際情勢が不安定になり、日中関係はこれまで以上に重要で、そして複雑になっています。中国を理解することは、東アジア、さらには世界を理解することにもつながります。
この演習では、中国の歴史と文化を中心に学びながら、日本社会と東アジア世界を多角的に考える力を養います。近現代中国の社会や文化に関するテキストを輪読し、討論や発表を通して理解を深めます。また、格差・貧困・ジェンダー・教育・メディアなど、現代社会を読み解くための幅広い視点を身につけます。あわせて、社会学・文化人類学・思想史などの理論的入門書を参照し、大学生としての教養を養いながら、複眼的に現代社会を理解する力を磨くことを目指します。
経済や社会の現象を、数字や制度だけでなく、人々の暮らしや文化のありかたのなかでとらえること――それが本ゼミの特徴です。輪読や討論、発表を通じて、幅広い視野と論理的思考力を身につけ、自分の言葉で社会を考え、伝える力を育てます。
たとえば、数年前に話題となった中国人観光客の「爆買い」現象があります。 その背景には、中国経済の成長や購買力の上昇といった数値的要因だけでなく、日本製品に対する信頼、贈答文化、人間関係を重んじる価値観といった文化的要素も関わっています。経済行動の背後には、常に社会や文化の文脈があるのです。
同じように、私たちが日常的に親しんでいる中華料理にも、移民と文化交流の歴史が刻まれています。
日本の街角の中華料理店で出されるラーメンや餃子(ギョーザ)、炒飯(チャーハン)の多くは、中国から移り住んだ人々が、日本の食材や味覚に合わせて工夫を重ねた結果として生まれたものです。彼らがいつ、なぜ、どのようなルートで日本にやってきたのかをたどると、当時の中国社会の状況や、日中関係、さらには国際関係のあり方が見えてきます。
こうして生まれた料理は、日本社会に受け入れられ、変化を重ねながら新しい食文化として定着していきました。つまり、身近な食文化の中にも、人の移動を通じた交流や、社会・国際関係の変化が映し出されているのです。
さらに、タピオカミルクティーの流行にも、台湾の製糖業の発展や、日本統治期に形成された甘味文化、そして現代のグローバルな消費文化が重なり合っています。こうした日常的な現象からも、アジアの近現代がもつ複雑で豊かなつながりが浮かび上がります。そして、そこには国や地域の違いを越えて共感できる、「おいしさ」という文化の力が息づいています。
本ゼミでは、このように身近な文化や社会現象を手がかりに、歴史と現在の関係を多角的に考察します。
過去を知ることを通して、私たちの生きる現在をより深く理解するとともに、日常のなかで見過ごしがちな出来事を複眼的に捉える力を養うことを目指します。
本ゼミは、中国や東アジアに関心のある人はもちろん、身近な社会の出来事をもう少し深く考えてみたい人や、経済と文化のつながりに興味のある人を歓迎します。
また、おしゃべりが好きな人も大歓迎です。
大学生活とは、社会に出るための準備段階であり、さまざまな経験を通じて自分を知り、他者を理解し、自分の可能性を広げていく時期だと考えています。だからこそ、目の前の課題をこなすだけでなく、大学生という特権のもとで「考える力」や「問いを立てる姿勢」を身につけてほしいと思います。
このゼミでの学びが、みなさん一人ひとりの思考を深め、次の一歩を考えるきっかけとなれば幸いです。そして、将来、みなさんがより広い世界で活躍できることを心から願っています。